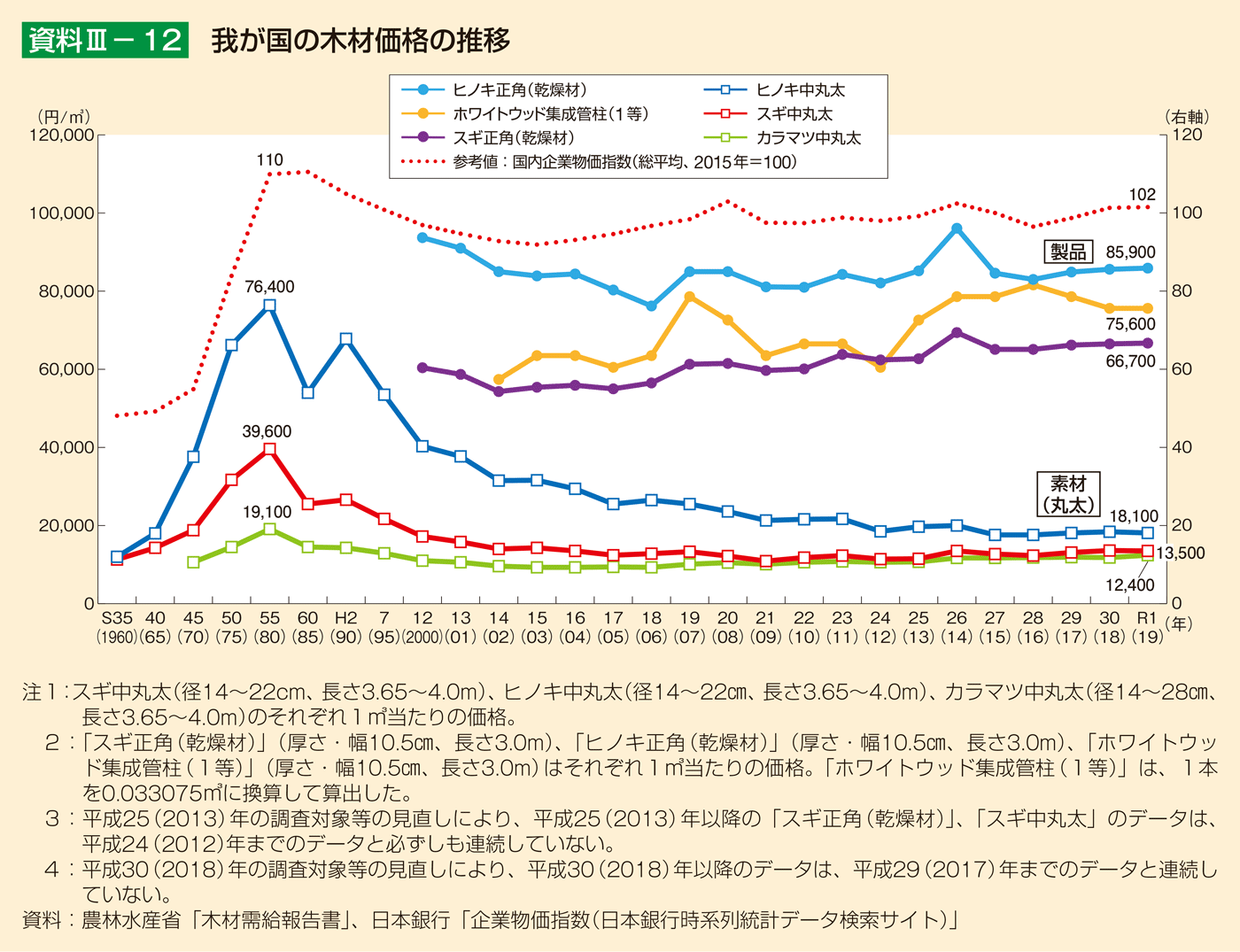国が後押しする木造建築

平成22年10月に「公共建築物などにおける木材の利用の促進に関する法律」が施行されました。
なぜこの法律ができたのかというと、森林を管理したり、木材を確保する林業が廃れないようにするため、木材全体の需要を拡大するためです。
また、老木や倒木を撤去するため、新しい樹木を植えて山を再生させるため、日本の伝統家屋の景観を守るためという目的もあります。
「樹木を伐採することを奨励するなんて、なんて法律だ」、「環境問題のことを考えていないのではないか」と思われるかもしれません。
林野庁によると、日本の森林面積は1966年から2017年の約50年で、ほぼ同じ数値を維持しています。
また、同庁によると森林面積は長い間同じ水準でしたが、森林蓄積は年々増え続けています。森林蓄積とは、森林資源量の目安のことです。
つまり、木材として活用できる木が増加しているのです。1966年から2017年までの51年間でみると、森林蓄積は約3倍に増加しています。
ちょっと古いデータですが、林野庁データを貼り付けておきます。
このデータからも分かる通り、日本列島では木が余りまくっています。
なぜ木が伐採されなくなったのかというと、木材の価格が下落したからです。
国産の材木の価格が低下した最大の理由は、木材輸入の自由化により、安い外国産の木材が入ってきたからです。
下図グラフは国産の木材の価格変動を表しています。このデータも林野庁のです。
昭和55年の価格をピークに下落し、ずっと横ばいになっているのが分かるかと思います。
価格が安くて材木があまり儲からなくなったのです。そのせいで樹木管理を行う林業が低迷し、伐採される木が少なくなってしまいました。
このような事態となったために冒頭でお話しした「公共建築物などにおける木材の利用の促進に関する法律」ができたのです。
つまり政府が、「木材の価格を上げるために木造建築をもっと積極的にやりましょう」という趣旨で動き出したのです。
「伐採される木が少なくなると環境問題にいい影響が出るのでは?」と思われるかもしれません。管理する人(山守)がいなくなるとちょっとやばいことになります。
ではどうなるのか?
それを次のブログで説明します。